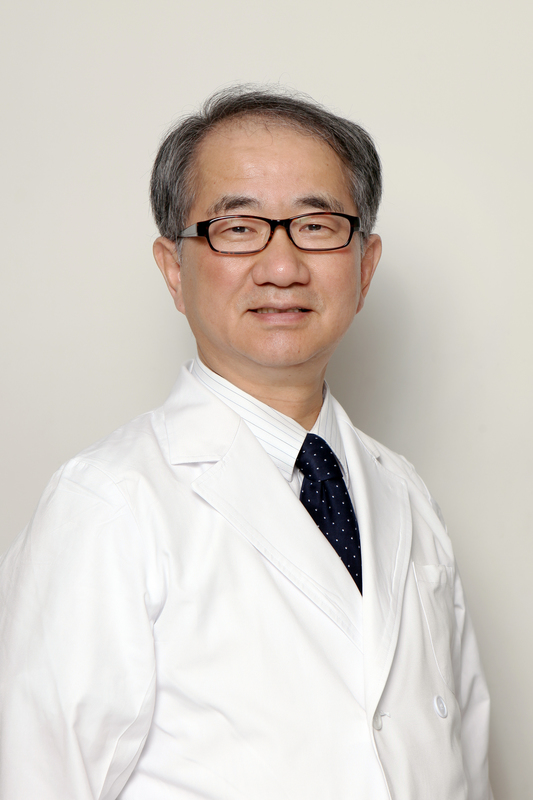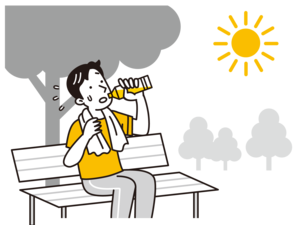Feature | 特集
原因不明の「川崎病」。0-4歳の乳幼児に増加しています
2017年 2月17日 11:59

川崎病は0歳から4歳の乳幼児によく起こる原因不明の疾患で、全身の血管に炎症を生じることが
特徴です。1967年に川崎富作がはじめて報告したことから、この名前が付きました。
日本での年間患者数は1万5,000人を超え、0~4歳人口あたりの罹患率は年々増加しています。
どんな症状?
・5日間以上続く発熱
・両側眼球結膜の充血
・口唇の紅潮、苺舌(舌が真っ赤になる)
・不定形発疹
・四肢末端の硬性浮腫
・非化膿性頸部リンパ節腫脹(くびのリンパ腺のはれ)
これらが主な症状で、5つがそろえば川崎病と診断されます。
4つしか該当しない場合でも、冠動脈瘤が発見されれば川崎病と診断されます。
合併症と予後
川崎病では全身の血管に炎症が生じます。発病から5日目以降に、心臓に栄養を送っている「冠動脈」に強い変化が見られます。治療がおそくなると、巨大な動脈瘤ができることがあります。
治療
グロブリンを大量に点滴静注することにより、冠動脈瘤の発症を25%→3%まで低減させることが
明らかとなり、血栓を予防する目的のアスピリンを併用するのが一般的です。
しかし、炎症が強くて動脈瘤の発症が予測される症例では、早期からステロイドなどの治療を追加して、より強力に治療を行います。
予後
軽度の血管炎で終息した例は2-3週目には正常化します。しかし、冠動脈瘤が後遺症として残った
場合は、心臓カテーテル等の検査が必要で、心臓の専門医の定期的な検診が絶対的に必要となります。